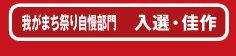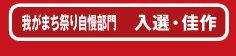|
 |
腕自慢部門 総評:
応募期間がわずか3ヶ月にも関わらず力作揃いでどれも甲乙つけがたく、審査日を1日延長して慎重に審査しました。
腕自慢部門ではシャッターチャンス、構図、プリントの出来具合、そして写真の持つ強さの写真力を審査し、平面の写真の奥にどのようなドラマがあるか、を感じさせるものが評価されます。同じ祭りに50点以上の応募が集中し、ほとんどの写真が似通ったハイライト場面のため、きわだって浮かびあがる作品が逆に少なくなってしまうものもありました。有名な祭りは見栄えがする場面が多いのですが、ぜひ独自の大胆な構図に挑んでください。また、せっかく良い構図でもプリントの出来が悪いために選外になった写真が多くありました。最終工程のプリント制作は納得がいくまでやりましょう。
日本には美しい四季があり、多様な宗教を受け入れた素晴らしい祭りがたくさんあります。祭りのエネルギーでぜひ日本に活力をいれたいものです。来年も力作をお待ちします。
我がまち祭り自慢部門 総評:
2Lサイズの写真での審査なので、コンパクトカメラによる撮影でも気軽に応募できます。技術面で構図が甘くても、多少プリントの色が悪くても構いません。ほのぼのとした雰囲気が伝わってくる写真や、画面を見て思わず微笑むような写真を求めています。家族が子供を見る視線で撮った写真や、思わぬ一瞬にユーモアが溢れるシャッターチャンスなど、スナップ写真歓迎の部門です。同じ写真を「我がまち祭り自慢部門」と「腕自慢部門」両方に応募されている方があったが、これはどちらかに決めましょう。また数十枚の家族アルバムのような写真を応募された方も何人かあったが、写真選びも技術の一つということを知っていただきたいと思います。一瞬のスナップを撮る場合は、いつでも撮れるように、シャッターチャンスを逃さないぞ、という気持ちでいましょう。来年も、気軽に撮った中からの、これはという作品をお待ちします。 |
|
はが ひなた/日本・世界の祭りの写真家。1978年成蹊大学法律学科卒業、1983年米国西イリノイ州立大学文科人類学科卒業。朝日新聞社「週刊日本の祭り」全30巻に「祭りを撮る」を連載。日本経済新聞社水曜夕刊「地球ハレの日」連載。2007年-2008年全国5都市のキヤノンギャラリーにて「世界のカーニバル」写真展開催。鹿児島市おはら祭審査委員長。(社)日本写真家協会、日本旅行作家協会会員。
芳賀日向公式サイト:http://hagafoto.jp/ |
|
 |
|
 |
 |
腕自慢部門 総評:
第1回目よりも応募数そのものはいくぶん少なかったようですが、むしろ内容的には前回に勝るとも劣らないレベルの作品が集まったように思います。
祭りや伝承行事というものは毎年粛々と繰り返されることに意義があり、新しい表現を求める写真コンテストの主旨とは相容れないように思われるかもしれませんが、その人ならではの見方や撮影アングルなど、独自のアプローチによる個性的な祭り写真が生み出される可能性はまだまだたくさんあるといえるはずです。
そういう意味で今回は、祭りそのものの目新しさだけではなく、よく知られた祭りであってもいかに新しい視点と解釈によって作品化されているか、といったことを主眼において作品を拝見しました。
我がまち祭り自慢部門 総評:
行事の形式を写すことを優先する純粋な記録写真は別として、祭り写真といえど、結局は人間そのものが生き生きと写っていなければ作品としての魅力は生まれません。この部門は、まさにそこにポイントを置いて撮られた作品を評価しました。結果的に上位に選ばれた作品を見直すと、それらの作品がやはり祭りの本質的なところをきっちり抑えた写真でもあったことは新しい発見でした。
全体の印象としては、インクジェットによる自家プリントでは色の彩度が高すぎるものが非常に目立ちました。過度に派手な色調は写真の内容を損ない、逆効果になると思ってください。 |
|
 |
| いたみ こうじ/福岡県生まれ。法政大学法学部卒業。写真愛好家向けの月刊誌「日本フォトコンテスト」の編集長を約20年務めたのち2004年に独立。長い編集者生活の中で、多くの写真作家と交流を持ち、写真界やカメラ界に詳しい。フォト・エディターとして、多くのコンテストや写真の審査にも参加。また、カメラ・光学・フィルムメーカーや写真雑誌編集者などで作る「業界写真クラブ」メンバーとして自らも撮影を楽しむ。社団法人日本写真協会(PSJ)会員。写真関連の企画・制作会社「Jophy Communications」代表。 |
|
|
 |
 |
腕自慢部門 総評:
全国各地から応募してきた写真をみわたすと、日本各地の祭りにはその地域ならではの特色があり、それがたいへん多種多様であることに改めて驚かされます。
予想以上に上手な作品が多く、甲乙つけがたいという印象がありました。しかし、そういうなかに思わず、心揺さぶられる写真があります。被写体についての知識も大事ですし、目にしたものを的確にとらえる技術も大事です。しかし、競い合いをつき抜けるためにはもう一つ、人の努力だけではかなわない不思議な力が必要だということでしょうか。今回の腕自慢部門で上位入賞した作品のなかには、奇跡とでも思うしか説明のつかない優れた写真が少なくありませんでした。
我がまち祭り自慢部門 総評:
プロの写真家はともかく、一般の人たちが最も多く被写体に選ぶのは自分の子供や孫の姿ではないでしょうか。家族写真には写真を撮る者と撮られる者の心の働きに無理がありません。はっとさせられた写真には、そうしたまなざしで写されたものが少なくありませんでした。
家族写真は写真を撮る目的が明快です。子供や孫にそれを見せて喜んで欲しいと思うから写真を撮るのです。まなざしを転じて、わが村や町の祭りにカメラとレンズをむける場合もそれと同じことが言えないでしょうか。村や町の年中行事で最もわくわくするのが祭りです。参加する人も見物する人も盛り上がります。ものを愛でる心の働きはおのずと形になって現れるものです。ふりかえってみますと、そうした写真がこの部門上位を占める結果になりました。 |
|
|
| ひらしま あきひこ/1946年千葉県生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。1969年毎日新聞社に入社。西部本社写真部をへて出版写真部に所属し、『毎日グラフ』『サンデー毎日』などの写真取材をする。出版写真部長、ビジュアル編集室長などを歴任。定年後、現在は出版企画室勤務。共著に『昭和二十年東京地図』『町の履歴書、神田を歩く』など。編集者として『宮本常一/写真・日記集成』、『グレートジャーニー全記録』(関野吉晴)、『1960年代の東京/路面電車の走る水の都の記憶』(池田信)などを担当。 |
|
 |
|