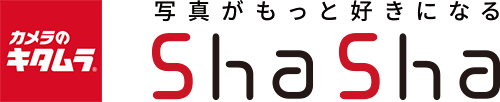星景写真の撮影テクニックと機材|齋藤朱門

はじめに
今回は星景写真撮影の撮影方法と必要な機材について紹介したいと思います。星景撮影は、3月から9月頃までは美しい天の川と風景を絡めて撮るのが醍醐味の一つです。また、冬の時期は空気が澄みますので、満天の星空と雪景色を撮るのも楽しいと思います。
星景写真を撮る

■撮影環境:マニュアル露出・16mm・F2.8・ISO3200・30秒
沖縄・宮古島の海岸で撮影した天の川です。国内での星の撮影で一番気にすべきことは光害の影響です。特に天の川のような銀河を撮影するためには、光の弱い星も多く撮影する必要があるため、光害の少ない宮古島のような離島や南端の海岸、山中のような街の光害の影響を受けにくい場所が適しています。新月期で光害の少ない場所であれば肉眼でも天の川を見て楽しむことができます。
設定のポイント
天の川を撮影する場合は、まずF2.8以下の明るいレンズを使うことをお薦めします。絞り設定は可能であればF2~F2.8程度にします。ISO感度は光害の状況によっても変える必要がありますが、高感度ノイズを考えるとISO1600-6400程度、シャッタースピードは20秒~30秒です。
気をつけるポイントとしては、焦点距離が長いレンズで長秒撮影を行うと、星の日周運動により、星が動くために、星が流れて線のように写ってしまう点があります。
実は、なるべく星を点として写すためのルールがあります。
「焦点距離 (mm) x シャッター時間(秒) < 500 」
これは通称 “500ルール”と呼ばれています。例えば、焦点距離が16mmの場合は 500/16 = 31.25なので、シャッター時間は約31秒以内とすれば良いことになります。
もし、50mmくらいの焦点距離で撮影する場合は、シャッター時間を10秒以内にしないと星が流れて線のように見えるので注意が必要です。(この場合明るいレンズ&ISO感度をあげることで10秒でも撮影可能です。)

■撮影環境:マニュアル露出・20mm・F2・ISO3200・15秒

■撮影環境:マニュアル露出・20mm・F2・ISO12800・3.2秒
灯台と天の川をした一枚。灯台の光が一定周期で回転するため、かなりシャッター時間を短くする必要がありました。そのため、ISO感度を12800まで上げています。
構図
星景撮影の場合、星と周りの風景をどう配置するかの構図が重要になります。天の川の場合はスマホアプリなどで天の川が見える方角を調べておくと良いでしょう。季節や時間によっても天の川の中心の出現位置や角度、方角が大きく異なるので注意が必要です。
特に8月くらいになると、早い時間に既に天の川が垂直に立ってきてしまうので、縦構図で撮る場合が多くなります。縦構図でも違和感のない構図、前景の場所で撮ると良いでしょう。

■撮影環境:マニュアル露出・15mm・F2.8・ISO6400・25秒

■撮影環境:マニュアル露出・24mm・F2.8・ISO6400・10秒

■撮影環境:マニュアル露出・20mm・F2.8・ISO3200・20秒

■撮影環境:マニュアル露出・20mm・F2.5・ISO5000・20秒
いろいろな撮り方
星景写真は季節や月齢によってさまざまな撮り方で楽しむことができます。
日周運動
北極星を中心に星の日周運動を撮るのも面白いと思います。日周運動を撮る場合は、バルブ撮影で数時間の長いシャッター時間にする方法と、連続撮影で数百枚の写真を撮り、それを後処理でスタックする方法の2つがあります。前者は一発撮りになるので失敗するリスクも高いため、筆者の場合は通常は後者の方法である連続撮影で撮影することが多いです。
連続撮影の場合は、カメラを連続撮影モードにした状態のままレリーズでシャッターボタンを押し続ける状態にすると比較的簡単に撮影することが可能です。
下の写真は八ヶ岳の北横岳で撮影。冬季だったため、雪に覆われた木々とともに星の日周運動を撮影。

■撮影環境:マニュアル露出・14mm・F2.4・ISO2500・25秒 x 76枚をスタック
こちらは富士山近郊での撮影。街が近く光害が強いため、ISO感度は低めに抑えています。

■撮影環境:マニュアル露出・20mm・F2.2・ISO800・30秒 x 120枚をスタック
月と絡める
星を撮影する場合、通常は月入り後から月の出までの月が出てない時間帯が適しています。満月期は明るい星以外は見えなくなりますが、新月期前後など、月齢によっては完全に星が見えなくなる前に月と星空を絡めて撮ることもできます。
宮古島の海岸で撮影。月の出とともに、空が明るく青くなってゆき、徐々に天の川も薄れていきました。

■撮影環境:マニュアル露出・20mm・F2.2・ISO800・30秒 x 120枚をスタック
燕岳で撮影。尾根の反対側から月が出始めており、雲を明るく照らしていました。

■撮影環境:マニュアル露出・20mm・F2.2・ISO800・30秒 x 120枚をスタック
パノラマ撮影
天の川は南から北に伸びているので、パノラマ撮影をすることも可能です。下の写真は上高地で撮影。縦構図で十数枚に分けて撮影したものをパノラマ合成しています。

■撮影環境:マニュアル露出・14mm・F2.8・ISO6400・20秒 x 12枚
必要な機材
星景撮影に必須もしくはあると便利な機材をいくつか紹介します。
三脚
長秒撮影になるため、三脚はほぼ必須です。お使いのカメラ・レンズの重量をしっかり支えられる、なるべくしっかりとブレない三脚を使うことをおすすめします。
タイマーレリーズ
カメラにタイマー機能が備わっている場合はなくても問題ないですが、備わってない場合はタイマーレリーズが必須となります。また、バルブ撮影時にも必要です。
レンズヒーター
冬に星撮影する場合は結露防止のために、レンズヒーターがあると便利です。USB給電のタイプが便利。
USBバッテリー
日周運動の撮影時など、長時間カメラの電源を入れた状態にすることがありますので、USBバッテリーがあると便利です。
赤道儀
筆者はあまり使いませんが、赤道儀があるとよりくっきりと鮮明に天の川等の銀河を撮影することができます。
ブライトモニタリング機能
機材ではないですが、ソニーのα7シリーズにある星景撮影に便利な機能を紹介しておきます。最近のα7シリーズには「ブライトモニタリング」という機能が備わっており、暗い中での構図決めに有効です。
周囲が暗い状況下での撮影で、構図合わせができるようにします。夜空などの暗い場所でも、露光時間を延ばすことにより、ビューファインダー/モニターで構図の確認ができます。
(α7IIIのヘルプガイドより抜粋)
さいごに
作例を交えながら星景写真の撮影方法やポイントをお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。星景撮影は天の川が醍醐味と思われる方も多いと思いますが、一年中さまざまな撮影方法で楽しめると思います。この記事が星景写真を撮影する際の参考になれば幸いです。
■写真家:齋藤朱門
宮城県出身。都内在住。2013年カリフォルニアにて、あるランドスケープフォトグラファーとの出会いをきっかけにカメラを手に取り活動を始める。海外での活動中に目にした作品の臨場感の素晴らしさに刺激を受け、自らがその場にいるかのような臨場感を出す撮影手法や現像技術の重要性を感じ、独学で風景写真を学ぶ。カメラ誌や書籍での執筆、Web等を通じて自身で学んだ撮影方法やRAW現像テクニックを公開中。
齋藤朱門さんの撮影テクニックの連載記事はこちら
・丘や山での撮影テクニック|齋藤朱門
https://www.kitamura.jp/shasha/article/483573391/
・滝・渓流での撮影テクニック|齋藤朱門
https://www.kitamura.jp/shasha/article/482531059/
・海での風景撮影テクニック|齋藤朱門
https://www.kitamura.jp/shasha/article/484586478/
・冬の風景撮影とテクニック|齋藤朱門
https://www.kitamura.jp/shasha/article/485081309/
・望遠ズームレンズで切り取る風景撮影の楽しみ方|齋藤朱門
https://www.kitamura.jp/shasha/article/485398095/