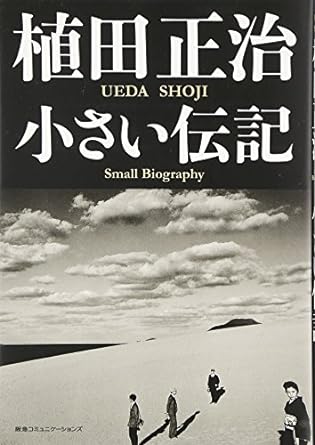【日本の名匠シリーズ 】植田正治とその時代 第二回「植田調」への道|1920~40年代 後編「田園詩人のよろこびと哀しみ」

はじめに
植田正治という写真家の不思議な魅力について、ときどき考え込んでしまうことがある。なぜ、私たちはその作品世界に惹かれてしまうのだろうか。生涯を「アマチュア」写真として生きた植田の作品は、時間や場所を超え、今なおファンを獲得し続けている。豊かな創造性の秘密に触れたくて、その歩みをこれからたどり直してみようと思う。
愛機ローライフレックスを手にして
1930年代初頭、植田正治は出発点となったピクトリアリズム、絵画調の芸術写真を基盤に、新しいムーブメントである新興写真や前衛写真を貪欲に消化し始めた。ただそれを山陰地方の小さな港町で実現するには、かなりの工夫を必要とした。
そもそも、この新しい芸術のムーブメントが展開されたのは、ベルリン、パリ、ニューヨーク、そしてモスクワという国際都市だった。それら都市がもつ幾何学的な造形や先進的な都市機能が、芸術家を触発し、またモダン・フォトグラフィのモチーフとなった。日本でも道路や鉄道網が整備されコンクリート製のビルディングが林立していった東京、大阪、名古屋などの大都市こそが、このムーブメントの中心だった。
例えば東京では堀野正雄、渡辺義雄、木村伊兵衛、土門拳、あるいは濱谷浩といった写真家を挙げることができる。彼らは新興写真を社会的な実践として高め、報道写真の系譜、いわばプロの世界をつくっていく写真家たちだ。一方、この時期に前衛写真であたらしい芸術写真をリードしたのは大阪を基盤にした安井仲治、小石清、中山岩太、ハナヤ勘兵衛らと、名古屋から登場する山本悍右や下郷羊雄といったアマチュアだった。
モダン都市を背景として、急速に育ちつつある表現に対して、田園地帯の穏やかな風景を造形的に活かした、新しい表現を生み出すにはどうすれば良いのか。この頃の植田は1934(昭和9)年に購入した中判の二眼レフ、シャープな描写をするテッサーF3.8のレンズが付いた「ローライフレックス」によってそれに取り組んでいた。
例えば逆光にカメラを向けた作品が目立ち、引いて撮った風景が減って中距離から対象を切り取るようになっている。徹底して構図を研究し、低めのアングルから人物を写した。とくに子どもを主役にした作品が多くを占めていくのもこの頃からだ。もともとスクエアフォーマットのカメラは、幾何学的な画面構成に適しているし、トリミングもやりやすい。なにより精細なローライフレックスの描写性能は、植田の作画の自由度を上げてくれたことだろう。そしてこのような試行錯誤のなかで見いだした最適解が、海辺での演出写真だったのだと思える。
代表作『少女四態』の発表
植田の努力の成果は1939(昭和14)年9月、東京の小西六本店のギャラリーで開かれた、第3回中国写真家集団展で示された。中国写真家集団とはその2年前に岡山、広島、鳥取の3県在住の実力派作家によって結成されたグループだ。発起人の石津良介は、岡山の有力なアマチュアであり、この後にはカメラ雑誌『カメラ』や『写真文化』の編集者として活躍する人物である。
中国写真家集団は年に一度、東京展を開催することを決めていたが、そこには中国地方ならではの「ローカルカラー」で、東京の新興写真ムーベメントに対抗する意図があったという。その3回目の展示で、植田は自ら初の演出写真と呼ぶ「少女四態」をはじめ「群童」「少女像」「猫」などを発表、なかでも「少女四態」はまさに東京の写真関係者を驚かせる出来栄えだった。
この横長のパノラマにトリミングされた作品は、夏服を着たおかっぱ頭の少女4人が砂浜の上に、水平かつ等間隔に配置されている。右端の少女は目を手に当てて泣き、他は無表情にそれぞれ遠く別の方角を向いている。3人はまっすぐに立っているが、右から2人目の少女だけは脚を抱えて座り、直線的な構図に視覚的アクセントを与えている。
少女をやや見上げるアングルは全体に凛とした雰囲気を醸し出し、同時にどこか甘酸っぱい感情を湧きあがらせてくれる。これは現実ではない夢の風景、ここではないどこかを描く、シュルレアリスム的なファンタジーだ。同年の『カメラ』誌11月号は、この作品を掲載するとともに展評欄でも大きな賛辞を与えている。
「植田正治氏の「少女四態」は正に圧巻である。この作品は(本誌口絵掲載)は非常に特殊な表現法を持ち、野心的な意図に依っているだけに、観る人に依っては強く反発し、まだ一方では一も二もなく受け入れると云った傾向があると思うが、何はともあれその好むと好まざるとに拘わらず、問題作たることを失はない。私はこの作品の批評は考えるところあって差控えるが、同氏の一つの飛躍そしてこの新しい分野をどう切り拓いていくか非常な期待と興味とをもって眺めて居たいと思う」
高評価を受けたものの、植田自身は展示の直前までひどいスランプに苦しんでいた。なんとか作品が仕上がったのは東京へ向かう前夜のことで、列車の中で石津らに初めて「少女四態」を見せるとみな目を疑ったという。それは苦しみ抜いた末に、ようやく活路が開けた瞬間だった。
さらに「少女四態」は大阪毎日新聞社主催の日本写真美術展でも特選を受賞し、植田への注目度もますます上がっていく。ただし、このとき温厚な植田を激怒させたできごとが起きている。
原因は同展の審査員で、写真界の権威だった森芳太郎が『写真新報』1940(昭和15)年2月号に書いた審査経過にあった。森は「少女四態」を、やはり芸術写真家の峰岸成光が1938(昭和13年)年に発表した「子供四態」の模倣だと断言し、それでも「模倣とは言え進歩工夫があったので黙過した」のだと高所から述べている。むろん植田にとって、これは身に覚えのない濡れ衣であり、プライドがひどく傷つけられた。
その悔しさはかなり長く尾を引いた。それから40年後の1980(昭和55)年、『カメラ毎日』11月号の連載「続・アマチュア諸君!」のなかでこう振り返っているのだ。
「まったく身に覚えのない偏見であり、謝罪文を要求しましたのでありましたが、握りつぶされ、それどころか、以降その批評家による私の写真は全然無視されるようになったというイキサツもございました。血の気の多い年齢だったのでしょう」
ただし森の名誉のために言えば、この「握りつぶされ」というのは事実ではない。森は翌々月号の『写真新報』で「少女四態の作者からの抗議」という一文を書き、そこで「軽率な断定をして甚だお気の毒であった。平にお詫びを申し上げる」と自らの誤解を認めている。植田はこれに気づかず、ずっと心に傷を抱えていたのだろうか。
とはいえ、この「少女四態」のヒントになった別の作品があったのは事実らしい。当時、植田が敬愛していた、日本光画協会の先達である渡辺淳の「三人乃少女」がそれにあたる。淡いソフトフォーカスで撮られた横長の画面に、白い服におかっぱ頭の3人の少女が配置された甘い夢のような優しさをもった作品だ。植田はこの作品について「本当にあどけない、純粋無垢な世界こそ、自分が表現したい世界を具現化して見せてくれた」のだと、島根県立美術館学芸員の蔦谷典子に何度も話していたという 。
「田園詩人」の憂鬱
「少女四態」の翌年、植田は「茶谷老人とその娘」、「群童」などを発表、またはじめての単行本である『田園の写し方』(アルス写真文庫)を出版した。同書は自作の解説を通じた技法書だが、なかに「僕は甘いといわれても構わない。いつでも田園に詩を求める男。『田園詩人』として生きたいんだ」といった独白などもあって味わい深い。
またカメラ雑誌に寄稿を求められることも増えた。例えば1939(昭和14)年『写真新報』3月号の「私の作画態度について」では、当時考えていたことを率直に書いている。ここでは「作家が同一のイズムの世界にいつ迄も安住して居て、他を顧みないという態度は可笑しなこと」だと語り、読者に対して変化することを恐れるなと呼び掛けている。自分がシュール・リアリストだとレッテルを貼られるのは迷惑でしかなく「作家は只作ればいい」のだと言いきってもいる。
確かに植田は、自らの写真の道を、この言葉の通り進んだのだ。好奇心のままに芸術写真、新興写真、前衛写真、写真館のポートレイト、後年はコンポラ写真などの要素を取り入れ、植田調を変奏させていったのだ。
とはいえ、この記事の直後には、自由な態度を止めざるを得ない時代がやってくる。1937(昭和12)年に始まった日中戦争は泥沼化しており、すでに言論や表現に対する圧力はただでさえ増していた。さらに1939(昭和14)年9月、第二次世界大戦が始まると、国内では政府主導の新体制運動が始まり、国民全体が相互監視的な状況におかれた。表現の自由はますます抑圧され、芸術写真に取り組むアマチュアへの締め付けも強まっていった。
植田の写真は、こうした戦時体制下でもカメラ雑誌のグラビアページを飾った。それは彼が「田園詩人」を自認する作家だったからかではないかと思う。当時のカメラ雑誌を見ていると、農村や田園地帯での撮影を勧める記事が目立つからだ。各種の法律によって撮影制限が厳しくなり、都市部ではカメラを持って歩くこともままならなくなっていた。カメラ雑誌はそこから田園地帯の撮影に、読者の目線を移すよう誘っている。だが、もちろんそんな状況下では、植田にしても満足のいく写真は撮りにくい。
そのことを端的に示すのが、1941(昭和16)年『写真文化』3月号に寄稿した「農村人物の写し方」だ。ここで植田は自分の演出写真について「故意に不自然に、演出その儘を画面に表す」ことで田園の素朴感を強調する、直立不動に加えて「更に生真面目な無表情の表情加えて、最も効果があると考えている」と語る。このことは「少女四態」を始めとする作品に当てはまるものだ。
だがその直後に、しかし「現在の時勢はもっと明るい、健康で、逞しい田園人を望んでいる」として、我々もそれを意識して撮っていかねばならないと自戒するのだ。さらに最近の田園地帯では、アマチュア写真家がスパイと疑われて連行される事例が続いていることに警鐘をならしている。何と取り繕おうが、こうした環境で植田の制作意欲が向上するわけもなかった。
さらにフィルムや機材の欠乏は顕著になり、カメラ雑誌も統廃合されて、発表メディアが縮小していった。アマチュア写真家たちも「興亜写真報国会」などの組織に組み込まれ、はっきり国家の戦時体制の歯車として働くことを余儀なくされる。植田もその例外ではいられず、最も暗い時代を迎えたのだった。
【次回へつづく】
※「日本の芸術写真──写真史における位置をめぐって」特別講演録(2011年4月16日)『東京都写真美術館紀要』十一号
引用は旧仮名遣いを直しています。
■執筆者:鳥原学
1965年、大阪市生まれ。近畿大学卒業。ギャラリー・アートグラフを経てフリーになり、おもに執筆活動と写真教育に携わっている。著書に『日本写真史(上・下)』(中公新書)、『教養としての写真全史』(筑摩選書)などがある。現在、日本写真芸術専門学校主任講師、武蔵野美術大学非常勤講師。2017年日本写真協会賞学芸賞受賞。